ソクラテスがテオドロスを相手に行った議論は、その趣旨からいえば、テアイテトスを相手にしたものと変わらなかった。つまりプロタゴラスの説とヘラクレイトスの説を反駁することなのである。なぜ、蒸し返しともいうべきことをソクラテスがあえてしたかというと、この二者の説が、知識は感覚に他ならないとする主張を裏付けるものと判断したからだろう。ソクラテス自身が、この議論の終わり近くでそのように述べている。プロタゴラスの、人間は万物の尺度であるという説は、個々の人間が自分の知覚=感覚するものこそ知識の源泉だとするものであるし、ヘラクレイトスの運動実有説は、万物が動いていることを直接的に知るものは感覚であると主張している。だからこの二者の説を反駁すれば、知識は感覚であるという主張への打撃になるだろう、とソクラテスは考えるのである。
















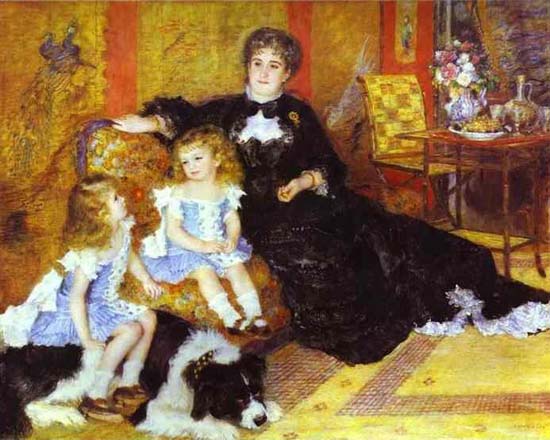

最近のコメント