「仮面の告白」は三島由紀夫の自伝的な作品だと言われている。たしかにこの作品には三島の実生活と深い関わりのある事柄が取り上げられている。兵役逃れと同性愛である。どちらも事実に裏打ちされているので、この作品を読んだ者は、三島が自分自身のことを語っていると思わされるだろう。その結果その読者が、三島に対してどのような感想を覚えるか。少なくとも、この小説が発表された当時には、好意的な受け止め方が多かった。兵役逃れのことはともかく、同性愛のことについては、これまでの日本の文学において取り上げられた例がほとんどなかったこともあって、なかばゲテ物趣味というか、型破りの小説として、既成の価値観が大きく揺らいでいた時代の雰囲気に乗じたということだったのかもしれない。




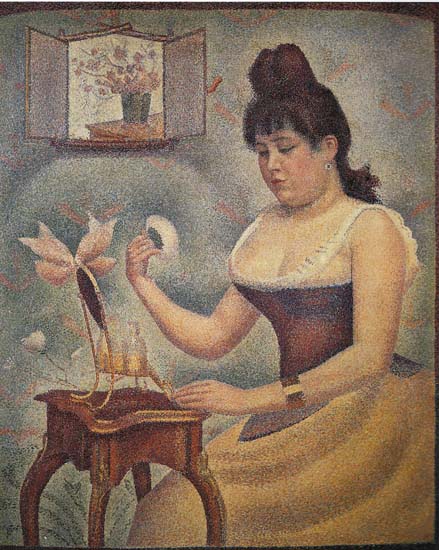






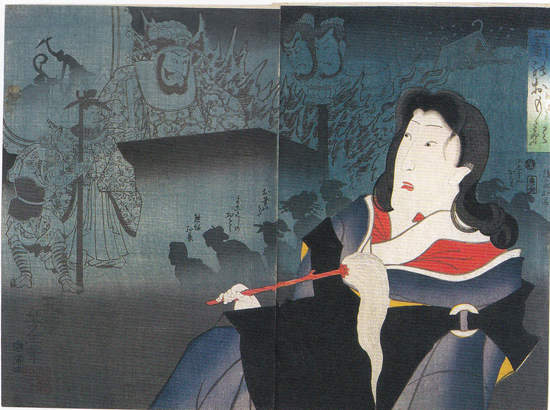


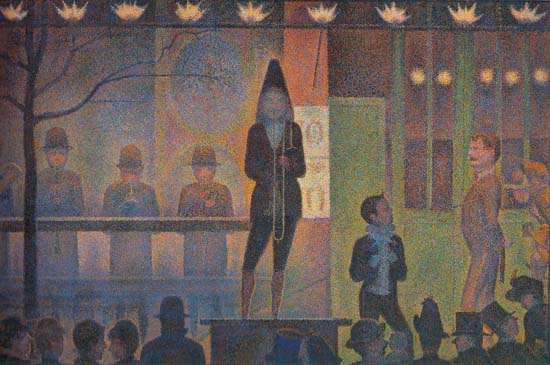








最近のコメント