学海先生の日記に妾の小蓮が初めて登場するのは明治六年二月二十一日である。
「小蓮とともに梅を墨水の梅荘に見る」と言う記事がそれである。
この日学海先生は小蓮を伴なって墨水の梅荘に梅を見に行き、そこで隠士と思しき三人が月琴・胡琴を演奏しているのを見た。興味を覚えて小蓮とともに聞き入っていると、更に別の一人が現れて一曲を弾じ、名を告げずして去った。
この当時、墨堤は根岸と並び隠士の遁世地として知られていた。記事に見える人たちもそうした隠士のような人だったように思われる。面白いのは学海先生が妾を伴いながら彼らを見て感興を覚えたことである。妾を伴っていればおそらく気分は晴れやかだったろう。その晴れやかな気分で隠士が琴を弾ずる模様を見れば、いっそうのびやかな気持ちになったに違いない。学海先生にはそういった風雅を愛するところがあった。


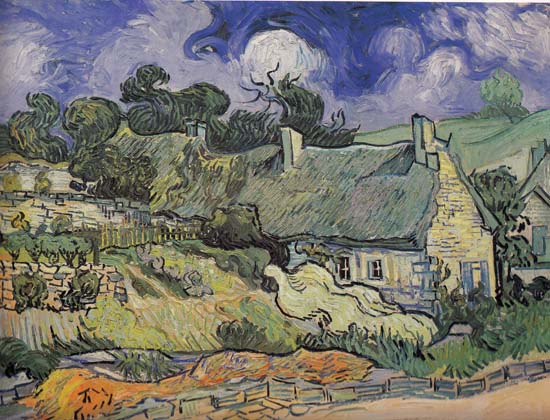













最近のコメント