毛利和子の近著「日中漂流」は、タイトルにあるとおり、21世紀に入って漂流する日中関係に大きな懸念を投げかけている。日中関係は、戦中戦後の不幸な時期を経て、日中国交正常化によって、一時期きわめて良好な関係を築いたかに見えたが、それも束の間のこと、21世紀に入ってからは、険悪な状況に陥り、政府関係はもとより国民感情のレベルにおいても、相手方への不信が高まって、かえって史上最悪の関係に陥っている。その関係は、近い将来武力衝突にも発展しかねない危うさを抱えている。そういう不幸な事態に陥らないために、両国、特に日本は何に心掛けねばならないか、そういった切羽詰まった毛利の問題意識が、この本からは切々と伝わって来る。


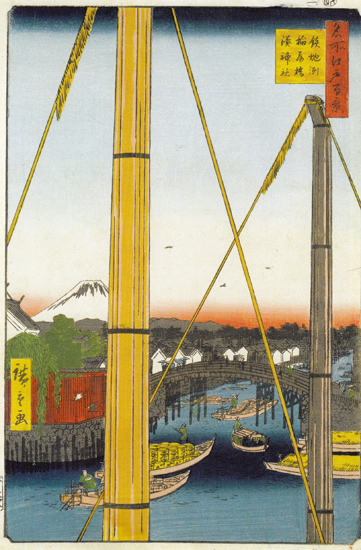















最近のコメント