ドゥルーズ=ガタリは、精神分析と分裂者分析とを資本主義分析の二つの対立しあう理論体系として捉える。分裂者分析という奇妙な言葉を発明したのはかれらだが、それはフロイトの精神分析に一定の敬意を払っているからだろう。精神分析は資本主義の従僕として、それに帰属し、資本主義の利益のために働く。それに対して、分裂者分析は、精神分析の虚偽性をあばき、精神分析が提示する欺瞞的な概念たるオイディプスに攻撃を加える。分裂者分析の役割は、なににもまして破壊にある、「破壊せよ。破壊せよ。分裂者分析の仕事は破壊を通じて行われる」(市倉訳)。分裂者分析は、「全力をあげて必要な破壊に専念しなければならないのだ。信仰や表象を、劇場の舞台を破壊せよ。そしてこの仕事に従事するためには、分裂者はいかに敵意ある活動をするとしても、決してしすぎるということにはならないであろう。オイディプスと去勢とを破壊せよ」。






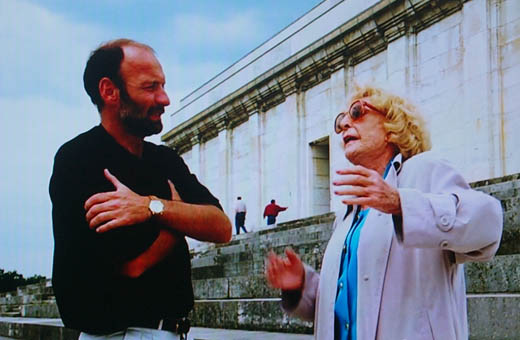




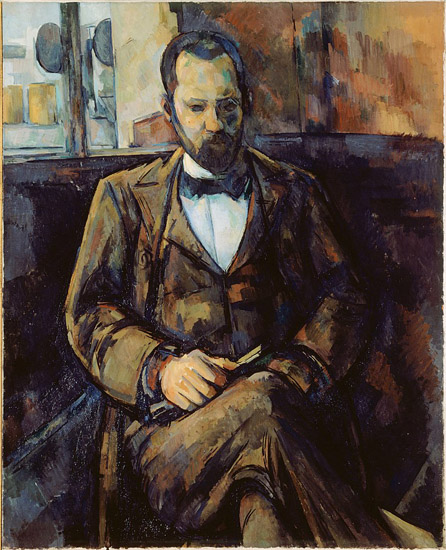

最近のコメント