菩薩の十地の第四は「光明に輝く菩薩の地」である。第三地から第四地に進みゆくにあたっては、十種のあらゆる存在についての光明(十法明門)を体得する。その十種の光明とは次のようなものである。
(1)あらゆる衆生をあらしめる衆生性(衆生界)をさまざまに思惟する光明
(2)あらゆる世界をあらしめる世界性(世界)をさまざまに思惟する光明
(3)あらゆる存在をあらしめる存在性(法界)をさまざまに思惟する光明
(4)空間をあらしめる空間性(虚空界)をさまざまに思惟する光明
(5)識をあらしめる識性(識界)をさまざまに思惟する光明
(6)欲望をあらしめる欲望性(欲界)をさまざまに思惟する光明
(7)物質のみが存在する禅定性(色界)をさまざまに思惟する光明
(8)物質も存在しなくなった禅定をあらしめる禅定性(無色界)をさまざまに思惟する光明
(9)広大な道心による信仰をあらしめる信仰性をさまざまに思惟する光明
(10)大乗の真理のままなる道心による信仰をあらしめる信仰性をさまざまに思惟する光明


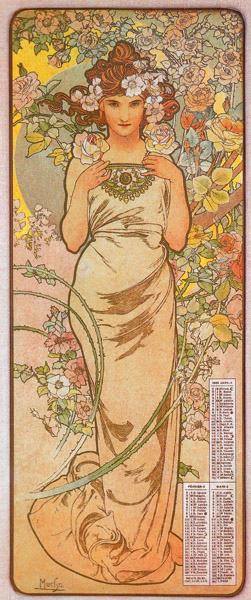



























最近のコメント