
2003年のギリシャ映画「タッチ・オブ・スパイス(Πολίτικη Κουζίνα タンス・プルメティス監督)」は、ギリシャ現代史の一齣を描いた作品。ギリシャ現代史については、テオ・アンゲロプロスが壮大な視点から俯瞰的に描いた映画があるが、これは、ギリシャとトルコの対立に焦点を当てたものだ。ギリシャとトルコは長らくキプロス島をめぐって対立してきた歴史があり、1955年と1964年には大規模な軍事衝突に発展した。一方、トルコの大都市コンスタンティノポリスには大勢のギリシャ人が暮らしており、そのギリシャ人がトルコによる迫害の対象になったりした。この映画は、迫害されてトルコを追われたギリシャ人家族の物語なのである。









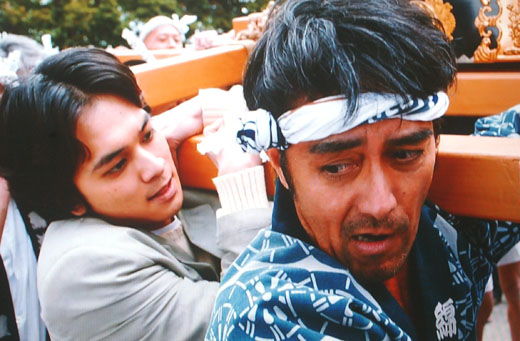
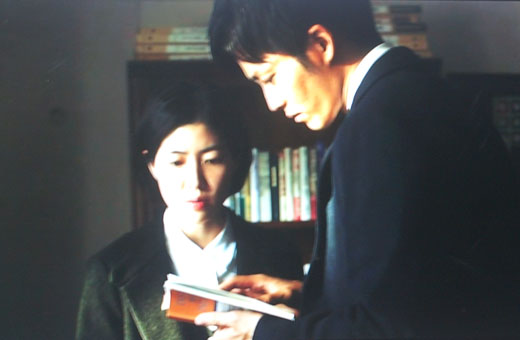








最近のコメント