トランプがパレスチナ問題に関する中東和平案を発表した。発表の場にはイスラエルのネタニアフが同席したが、パレスチナ側は不在だった。その事態が象徴しているように、この和平案なるものは、イスラエルの言い分を一方的に聞いたようなもので、パレスチナ側は全面拒否の姿勢を見せている。たしかに、パレスチナ側の反発は理解できる。この案は、イスラエルによるこれまでの不法な入植をすべて認め、また、エルサレムを全面的にイスラエルに帰属させるなど、イスラエルの無法な占領にお墨付きを与える一方、パレスチナ側には「テロ(抵抗行為のこと)」の自重を促すものだ。要するに、パレスチナはこれまでに積み上げられて来た現実(無法なものだが)をすべて受け入れよと迫るものだ。




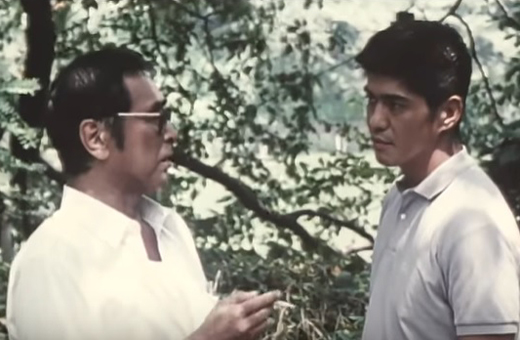

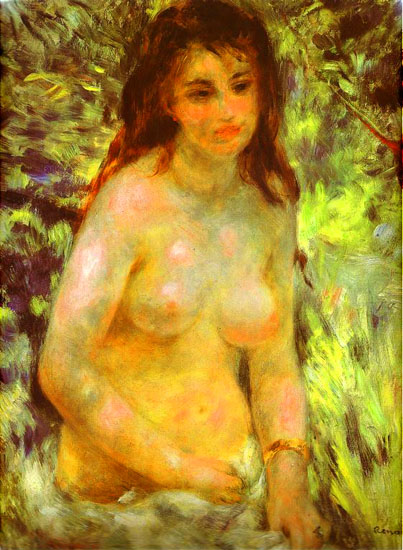
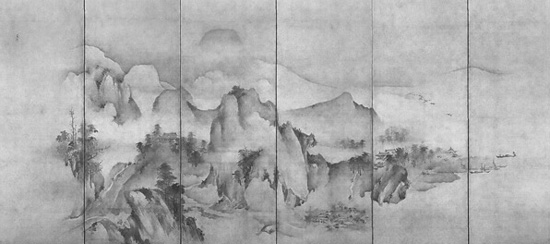










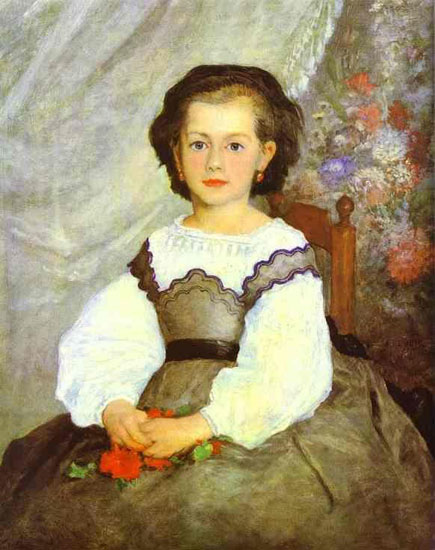

最近のコメント